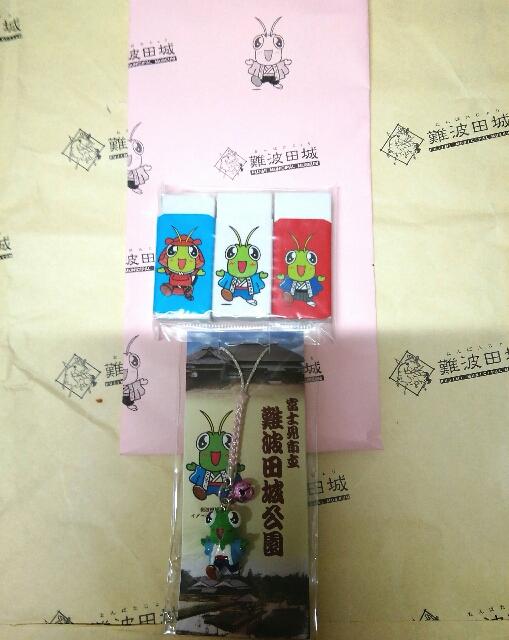0

榛名神社由緒を読み写す。
榛名神社由緒
勝瀬総鎮守
御祭神 埴山姫命(土・植物を司る神)
豊受姫命(食物を司る神)
年中祭事 1月1日 元旦祭
2月3日 節分祭
2月20日 祈年祭(豊作・諸事繁栄祈願祭)
3月初午日 稲荷社祭(初午)
4月10日 例大祭(神楽・囃子・植木市・露店)
5月1日 塞祭
5月10日 苗木市
7月28日 夏越大祓式(茅の輪くぐり)
11月適宜日 七五三
11月20日 新嘗祭(新穀・諸事感謝祭)
12月冬至日 冬至星祭
12月28日 釜しめ 頒布
由緒 詳細創立年代は不明。本社再建が文明9暦丁酉年(室町中期 西暦1477年)4月10日武州入東郡勝瀬村大願主林光防武州吉見領小泉村大工加藤杢之助と棟札に明記されている。川越城主松平大和守の崇敬あり毎年御供米一斗五升宛下附せられた。明治5年村社に列した(明治39年4月神饌弊帛料供進指定)
伝説 当社の創建に関する地元の言伝え「お船山伝説」あり。一説は、昔この辺が海だった頃、榛名大神がお供のお二人方をお連れになり、船に乗られ遠くからここに来られました。船は無事に岸辺(現在の榛名神社の南端にあたる海岸線)に到着し、めざす陸地に上がることができました。岸辺に繫いでおいた船はいつか岸から離れ、海上を漂い、「お船山(神社南方約100mにある地)」に沈みました。ちなみにお連れは船頭の鷺森大権現様と大弁財天女様です。
もう一説は、一行の船がお船山で沈み困ったが、神社南端の岸辺からのびていた大きな藤の木の蔦を伝って神様達が陸に上がりこの地に鎮座されたという説もあります。ちなみに神仏習合時代の榛名様を「日本藤島榛名満行大権現」と言った。
境内および境外地 約2570坪
摂末社
稲荷神社 祭神 宇迦御魂命 例祭旧暦2月初午。天明3年(西暦1783年)建立と伝わる。明治40年6月5日字稲荷窪の稲荷社、稲荷前の稲荷社、屋敷廻りの稲荷社を合祀。その後複数の稲荷社を統合、合祀。
厳島神社 祭神 市杵島姫命 創立年月不詳 享和壬戌年4月当村塩野源右衛門再営の棟札がある。船山弁財天と称したが明治7年5月、社名を改め当字谷田、お船山より遷座。明治41年6月17日、お船山より石碑をこの隣地に移転。
富士神社 祭神 木花開耶姫命 明治41年年6月13日当字茶立久保、オトウカ山より移転。
藤塚神社 祭神 稚産霊命 創立年月不明。寛政6年(西暦1794年)3月吉田願主塩野半平再建すとある。
大穴天神社 祭神 大己貴命 創立年月不明。昭和27年5月社殿改築。
疱瘡神社 祭神 大禍津日命 安永年間(西日本を虫害が襲った享保の大飢饉、東北地方等の冷害を発端とする天明の大飢饉の時代)村内にて建立したと伝えている。
信仰
万物育成 諸々増殖 大地守護 五穀豊穣 食物守護 厠守護。